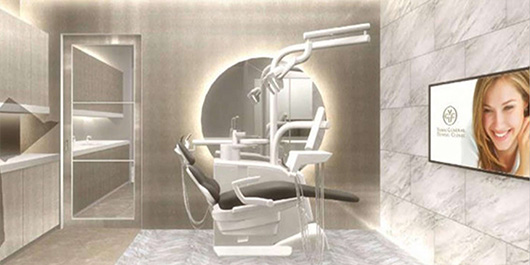歯並びをきれいに整えたいと考える方は多いですが、その背景には顎の位置が深く関係しているのをご存知ですか?
実は顎の位置は噛み合わせや全身のバランスにまで影響します。
矯正治療では歯列を並べるだけでなく、正しい顎の位置を獲得することも重要な目的のひとつです。
ここでは、正しい顎の位置とは何かを中心咬合位や中心位といった基準を交えて解説し、そのずれがもたらすリスクや矯正治療による改善について紹介します。
目次
■正しい顎の位置とは?
◎中心咬合位と中心位
中心咬合位(ちゅうしんこうごうい)とは、上下の歯が自然に最大面積で接触し、噛み合っている状態を指します。
一方、中心位とは歯の接触ではなく、顎関節が関節の中で安定している位置を意味します。
これを踏まえて、一番良い顎の位置とは、歯が最大面積で当たっている時、顎の位置に無理がないことを指します。
両者のずれが大きいと、歯や関節に無理な力がかかり、さまざまなトラブルの原因となります。
■顎の位置がずれる原因
◎骨格や遺伝の影響
親から受け継いだ骨格の形や歯の大きさによって、顎の位置がずれやすくなることがあります。
上下の顎の大きさや前後のバランスが合っていないと、噛み合わせがずれてしまい、顎関節にも余計な力が加わります。
遺伝的な要因は本人の努力だけではコントロールできないため、矯正治療などで適切に整えることが必要になります。
◎悪癖
指しゃぶり、口呼吸、頬杖などの習慣は、成長期の顎の発育に影響します。
例えば、口呼吸が続くと舌の位置が下がり、上顎の発達が不十分になることで歯並びや顎の位置に影響します。
頬杖も片側だけに負担をかけるため、顎が左右にずれる原因となります。
癖は後天的な要因として代表的であり、生活習慣の見直しが予防につながります。
◎歯の欠損や不正咬合
歯を失ったまま放置したり、もともとの噛み合わせに乱れがあったりすると、顎の位置がずれていきやすくなります。
失った歯のスペースに隣の歯が倒れ込んだり、噛み合わせがずれて片側だけで噛む癖がついたりすることで、顎関節や筋肉に負担が集中します。
特に奥歯を失うと、噛むバランスが大きく崩れやすいため注意が必要です。
■顎の位置がずれていると起こる問題
◎噛みにくさ
顎の位置が不安定だと、一部の歯に強い力が集中します。
これにより歯の摩耗や破折のリスクが高くなるだけでなく、しっかり噛めないことから消化不良を起こすこともあります。
◎顎関節症
中心咬合位と中心位のずれが大きいと、関節や筋肉に負担がかかり、口の開閉時に音が鳴る、痛みやだるさを感じるなどの顎関節症を発症することがあります。
症状が進行すると、口が開けにくい、頭痛や肩こりを伴うといった全身的な不調にもつながる可能性があります。
◎姿勢や全身への影響
お口周りの筋肉は首や肩の筋肉と連動しているため、顎のずれは肩こりや頭痛、姿勢の歪みにもつながる可能性があります。
特に長時間のデスクワークやスマホ使用などで姿勢が悪い方は、顎のずれと姿勢の悪化が相互に影響し合い、不調が慢性化することもあります。
■矯正で直せる?矯正に及ぼす影響とは
◎噛み合わせは矯正で治せる
矯正治療では、単に歯をきれいに並べるだけでなく、上下の噛み合わせを正しい位置に導くことが可能です。
特に全顎的な矯正を行うことで、見た目だけでなく機能的に噛める状態を目指すことができます。
◎噛み合わせが悪いままだと?
歯並びをきれいに整えても、噛み合わせが悪い状態だと矯正後に歯が後戻りしてしまうリスクがあります。
さらに、顎関節に負担がかかり続けるため、矯正治療後でも顎関節症の症状が出ることもあります。
【歯並びと同じように大切な噛み合わせ】
正しい顎の位置とは、歯が最大面積で噛み合う中心咬合位と、顎関節が安定する中心位の差が小さく、歯と関節の両方に負担のない状態を指します。
ずれが大きいと、噛み合わせの不具合や顎関節症、さらには全身にも良くない影響があります。
矯正治療によって正しい顎の位置を得ることによって噛む機能や健康の向上につながります。特に全顎的な治療を行うことで、歯並びと噛み合わせの両方を安定させることができます。